おのなびの
おすすめ
尾道
ぶらり尾道探検隊|
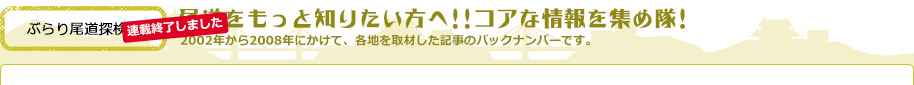


6年間に渡って取材した尾道の情報アーカイブです。情報が古いものもありますが、まだまだ使える情報が盛りだくさん。まずは読んでみてね。

2004年12月号:Vol.30
西国寺(さいこくじ)火渡りで厄払い!
西国寺 火渡り 柴燈護摩

師走に入り皆さんなんとなく気ぜわしくなってきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?
今回のぶらりは今年を飛び越え、新春の風物詩、西國寺の火渡り神事として有名な「柴燈護摩」をクローズアップします。
そのほか年末年始の特別企画もちょこっとだけ紹介しますのでお見逃しなく!
●尾道は西国寺。
尾道の古寺めぐりコースの中でも特に有名なこの西國寺。大ぞうりで有名な仁王門があるお寺というとピンと来る人も多いのではないでしょうか。
(詳しくは「ぶらり」のバックナンバー2003年12月で)
このお寺では毎年1月8日に「柴燈護摩」という護摩の神事が行われます。

【護摩(ごま)ってなに?】
そもそも護摩とは何でしょう?
開けゴマのゴマ?そんなの知らないって言わないでちょっとばかりお付き合いを…。
昔、「分からないことがあれば辞書を引け」と先生によく言われた担当D、さっそく辞書を引いてみました。 ふむふむ…。

【梵homaの音写で焚焼(ふんしよう)・火祭りの意】…密教で、不動明王明王などの前に壇を築き、火炉(かろ)を設けての木などを燃やし、煩悩(ぼんのう)を焼却し、併せて息災祈願する修法
とありました。
う〜ん、ちょっと難しいですね。
でもなんとなく火を焚くことによって悪いものを取り去り、幸福を祈るって感じは分かりますね。

【護摩と『柴燈護摩』の違いってなに?】
で、「護摩」と「柴燈護摩」とは何が違うんでしょうか。
「柴燈護摩」とは修験者が修行で山に登った際、薪や木の枝(柴)などを焚いて護摩修行したというところから起こっているようです。お寺で行う際には屋外にヒノキの枝などを積み行います。
違いを大雑把に言うと屋内で行うのが「(内)護摩」、外で行う護摩を「柴燈護摩」ということでしょうか。

【火渡り始まる!!】
柴燈護摩は法要や護摩木へ点火の儀式が行われた後、いよいよこの行事のクライマックスでもある「火渡り神事」が始まります。
この火渡り神事は家内安全、健康祈願など1年の大安をお祈りする儀式ですが、名前の通り燃えている護摩木の上を裸足で渡りきる、というなんとも熱そうな荒行です。

長さ約10m。この間をお祈りしながら一気に渡りきります。
はじめは住職さん、それに続き修験者が渡り、最後に一般の参加者の火渡りが行われます。毎年数百人がこの火渡りを行うそうです。

【凛とした空気漂う火渡り】
周囲はいぶされたヒノキの香りと煙で包まれ、凛とした静寂な空気が時間を支配しているような錯覚に陥ります。

その中で次々に渡っていく人たちを見ていると火の熱さというより、その人たちの祈りの深さを感じてしまいます。
渡りきった人の顔を見てみると清々しい顔をしておられるのが印象的です。

【何万回と聞かれる質問】
「これって火傷しないのかな?」と思い、以前渡ったことのある方にお話を伺ったことがあるのですが、「やっぱり熱いですがやけどはしません。渡りきったあとはすっきりした気持ちになりますよ」とのことでした。

渡ってみたいけど怖い、っていう人は後のほうに渡ってみると大丈夫と思いますよ。
一年のお祈りを込めて1月8日は西國寺で火渡りを体験してみませんか?

【「尾道七佛めぐり」よりお知らせ】
毎年元日から「尾道七佛めぐり」をして7か寺の朱印すべて集められた方には先着で毎年好評をいただいている「特製干支色紙」をプレゼントいたします。
この色紙は「沈黙の艦隊」の作者で知られる「かわぐちかいじ」さんの弟で、尾道で活躍されている漫画家「かわぐちきょうじ」さんにより描かれている個性的な色紙です。
数が限定なので、ほしい人は早めに!!
【西国寺・柴燈護摩は…】
場 所: 尾道市西久保町 西國寺
開催日時: 毎年1月8日 11:00〜12:30
入壇料(火渡り参加料): 1,500円(はちまき、御幣〔ごへい〕のお守りを含む)
お問合せ先: 西國寺 0848−37−0321
アクセス: バス、タクシーなどでお越しになると便利です。








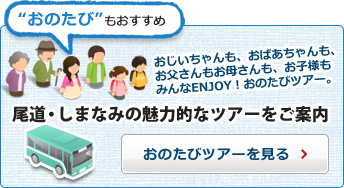
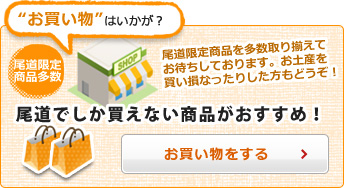
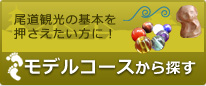



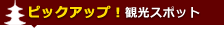





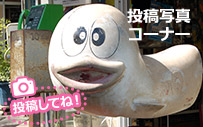 投稿写真コーナー
投稿写真コーナー


